交通事故の可能性は、誰にでも起こり得る
交通事故は、車を運転する方なら、誰しもが起こす可能性がありますし、歩いているだけでも交通事故に遭遇してしまう可能性は誰でもが持っています。
交通事故の事後処理や損害回復などで、専門家を探そうとすると、色々専門家がいて迷ってしまうと思います。
交通事故を何回も・・・?という不幸な経験がある方は少ないとは思いますが、一度経験をした方ならその大変さは、お分かりですよね!
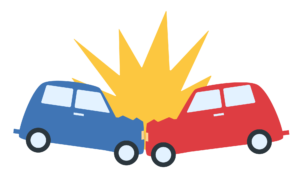 突然の災難で、右も左もわからずに処理をして無駄な時間と費用を掛け、後で後悔したというような話もよく耳にします。
突然の災難で、右も左もわからずに処理をして無駄な時間と費用を掛け、後で後悔したというような話もよく耳にします。
行政書士が、交通事故に関わるのは『自賠責保険』への手続きとしてです。
弁護士が交通事故に関わるのは『加害者(保険会社)』に対しての交渉人としてです。
ですから、行政書士の交通事故業務は、自賠責保険への手続きで、後遺障害の適正な認定を受けようとするものが中心になります。
弁護士の交通事故業務は、示談金の金額を交渉などが中心で、訴訟も視野に入ります。
これから症状固定や、後遺障害認定をと思えば、まずは行政書士を訪ねてみるといいと思います。
後遺障害など無い、もしくは、すでに認められている、物損のみの事故、過失割合の主張に大きな隔たりがある、最初から裁判する気マンマンの場合などは、弁護士が良いのかなと思います。
交通事故に遭遇したなら・・・!
交通事故に遭遇した場合の措置
1.自動車を止めて、事故の状況を確認します。
2.負傷者を救護します。
3.道路上の危険防止措置をとります。
4.警察へ事故を報告します。
【あなたが被害者の場合の措置】
☆加害者と対象車の確認
・運転免許証を提示させて、加害者の氏名、住所をメモし、電話番号を聞きます。
・名刺などをもらい、勤務先の名称、連絡先を確認します。
・加害車両のナンバーを確認し、メモします。
・自動車の所有者や管理者が加害者とは異なる場合には、その氏名、連絡先、運転の目的などを確認します。
・車体に会社名などが書かれている場合は、これをメモします。
・自賠責保険証および任意保険証を見せてもらうなどして、保険会社の名称および証明書番号を確認します。
2.事故現場の状況を確認します。
加害者が、事故直後には認めていたことを、警察官が来た時や、示談の時には否定する、ということがよくあります。 また、被害者が救急車で運ばれたりすると、被害者がいないことをいいことに、道路上の危険防止措置をとるふりをして、証拠を隠蔽したりすることがあります。 それを防ぐため、目撃者がいる場合は、住所、氏名、連絡先、証言内容をメモします。
怪我がひどく、動けない場合でも、携帯電話やスマートフォンなどのカメラ機能で、車から見える範囲を写真に撮れば、自分の車の位置などを把握することができます。
できれば、加害車両の写真も撮っておくようにしまよう。 こうすることで、道路上の危険防止措置として、車両が動かされたあとでも、事故直後の被害車両、加害車両の位置関係がはっきりします。また、後日、現場に赴き、スリップ痕、見通し、ガードレール等の物損状況を確認する必要もあります。
3.警察へ通報します。
警察への通報は、通常、加害者の義務ですが、加害者の仕事の都合、免許証の点数が残り少ないなどの理由で、警察へ通報することを拒む、もしくは、通報しないよう、懇願されることがあります。 しかし、それを受け入れると、交通事故証明書が発行できない、警察官による現場検証が行われず、証拠が残らないことになり、それをいいことに、加害者に有利に示談を運ばれることになりがちです。
どんな軽微な事故でも、必ず警察へ通報しましょう。
※事故現場でしてはならないこと。
加害者側としては、すぐに示談をしない、事故の原因は全て自分にあり、被害者の損害を全て賠償する、というような念書を書かない、ということが挙げられます。
示談は、やり直しがききませんので、安易に、すぐしてしまうのはよくありません。 念書も、事故当時は、正確な状況判断が出来ず、過失割合もわからないままに全ての責任を負うと誓約するのは、よくありません。
被害者側としても、やはり示談をすぐにしない、怪我が 軽いからといって、検査もせずに、事故を物損扱いにしない!ということが挙げられます。
その時は、怪我が軽いと思っても、思わぬ後遺症がでることもあります。
注意:加害者側としては、人身事故を避け物損扱いにしたいという気持ちで早く片付けようとする傾向があります。
必ず、病院で検査を受けるようにしましょう。
整骨院で診療を受ける場合でも、まず、病院で検査を受け、病院の指示があってから、整骨院に行くようにしましょう。 整骨院通院中も、定期的に病院で診療を受け、自身の体を状態を医師に確認させておきます。
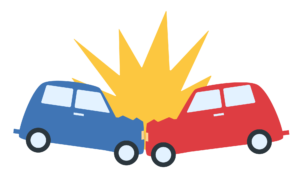 突然の災難で、
突然の災難で、
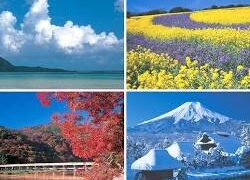

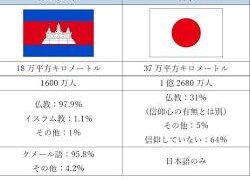
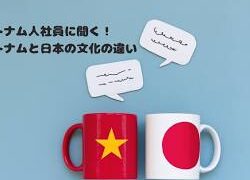
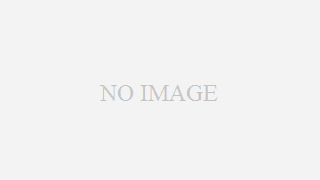












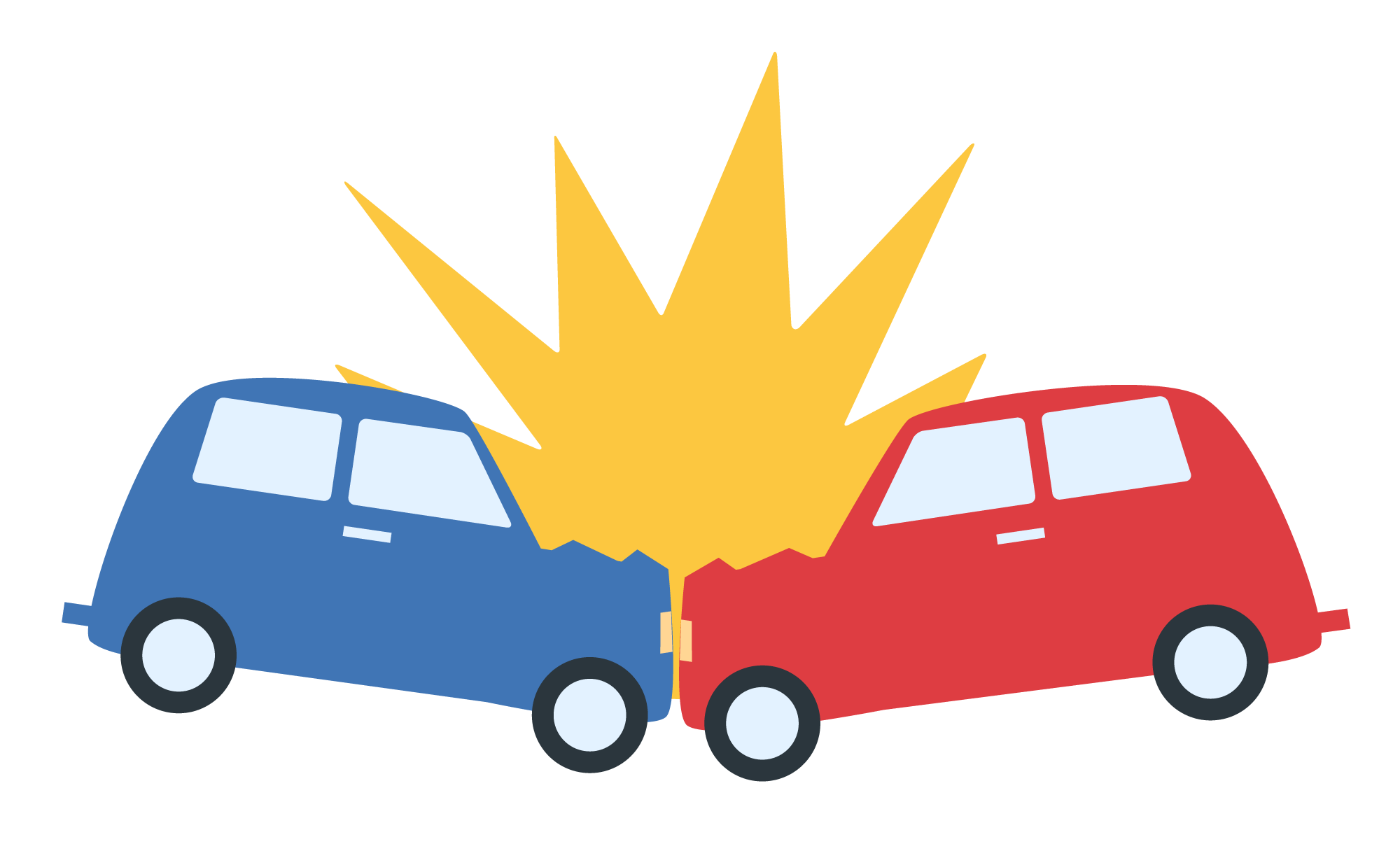


コメント