結婚ビザを取得するには ~ 失敗しないための重要なポイント!!
 これから結婚ビザの申請をお考えの方はもちろんのこと、既に申請したけれども不許可(不交付)となってしまった方に、是非、これだけは知っておいていただきたいことがあります。
これから結婚ビザの申請をお考えの方はもちろんのこと、既に申請したけれども不許可(不交付)となってしまった方に、是非、これだけは知っておいていただきたいことがあります。
それは、申請した結果が許可となったり、不許可となったりするその理由、その原因はどこにあるのか?ということです。
結婚ビザを取得するには、入国管理局所定の申請書に必要事項を記入し、戸籍謄本などの必要書類を揃えて、住所地を管轄する地方入国管理局に対して申請します。
入国管理局は、提出された申請書類をもとに、ある一定の審査基準(許可要件)に基づいて審査を行い、その可否を判断します。
失敗する人の多くに共通するのは、このことをよく理解していないため、一つ一つの意味をよく考えないで書類を作成し、必要書類を揃えて、何のためらいもなくそのまま提出してしまいます。
その結果、入国管理局から届いた知らせが、不許可の通知書だったり、在留資格認定証明書の不交付通知書だったりするのです。
そこで、こうした失敗をしないためには、あらかじめ審査基準(許可要件)の内容をよく理解し、確実に許可を取得するための書類を作成して申請を行う必要があります。
このホームページでは、許可・不許可となる理由を明らかにするとともに、結婚ビザを確実に取得するための具体的な方法についても、わかりやすくご紹介します。
1回の申請で確実に結婚ビザを取得したい方、これまで何度も申請したけれども許可されず諦めかけていた方、そういう方は諦めないで、是非、最後までお読みください。
結婚ビザとは
外国人の方が日本に入国して、何らかの活動を行なうには、その活動内容に見合った「在留資格」を取得する必要があります。
在留資格とは、日本に滞在(「在留」ともいいます。)する外国人について、入管法で定めるその在留に関する一定の資格のことをいいます。
たとえば、日本の大学で学ぶ留学生は「留学」という在留資格を、また、日本の会社に雇用されてシステムエンジニアとして働くためには 「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をそれぞれ取得する必要があります。
同じように、外国人の方が日本人の方と結婚して日本で一緒に生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。
日本人と結婚した外国人の方が日本で暮らすために必要となるビザのことを「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」と呼んだりしていますが、 正式には、この「日本人の配偶者等」という在留資格のことを指します。
結婚ビザ取得の方法には、3つのルートがある!
結婚ビザを取得するための手続きには、次ぎの3つの方法があります。
(1) 在留資格認定証明書交付申請
一つは、現在、海外で暮らしている外国人の配偶者とこれから日本で一緒に生活するため、外国人配偶者を日本に呼び寄せる(呼び寄せることを「招聘」 といいます。)ことを目的に行なう「在留資格認定証明書交付申請」と呼ばれる手続です。
(2) 在留資格変更許可申請
二つめは、現在、外国人の配偶者が他の在留資格で日本に在留している場合に、結婚ビザへの変更を行なうための「在留資格変更許可申請」と呼ばれる手続です。
たとえば、外国人留学生が日本人と結婚して、「留学」から「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更する場合がこれです。
(3) 在留特別許可制度
三つめは、現在、日本にいる非正規滞在者(オーバースティや密入国者)が日本人と結婚して、引き続き在留を希望して入国管理局へ自ら出頭し、退去強制手続きの中で特別に在留の許可が認められる「在留特別許可」と呼ばれる手続です。
次の項では、海外で暮らしている外国人配偶者を日本に呼び寄せるために行なう「在留資格認定証明書交付申請」の手続きについて説明します。
外国人配偶者を日本へ招聘するには!
「在留資格認定証明書交付申請」という手続は、日本人配偶者が外国にいる外国人配偶者を日本に招聘するため、 地方入国管理局に対して「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に入国及び在留する許可を求める手続きです。
具体的には、日本人配偶者が入管所定の「在留資格認定証明書交付申請書」に必要事項を記入し、戸籍謄本などの必要書類を添付 して、お住まいの住所地を管轄する地方入国管理局に対して申請します。
入国管理局は、提出された申請書類をもとに、申請内容を審査基準(許可要件)に従って審査し、その可否を決定します。
また、審査の途中で、不明な点があれば、資料の追加提出を求めたり、書面で説明を求めたり、あるいは、必要に応じて電話による確認や実態調査を行います。
そして、申請内容に問題がなければ、「在留資格認定証明書」という書類が交付され、郵便で送られてきます。
審査に要する期間は、最も早いケースで約10日間、時間のかかるケースだと、4、5か月から半年以上かかるケースもありますが、標準的な審査期間は、おおむね1か月から3か月程度です。
「在留資格認定証明書」が届いたら、それを外国人配偶者のもとへ送り、現地の日本総領事館に査証(ビザ)の申請をします。
そして、査証(ビザ)が無事に発給されると、パスポートに査証(ビザ)のシールが貼られ、そのパスポートと「在留資格認定証明書」を持って、日本に向け出発し、上陸する空港で入国審査を受けます。
入国審査をパスすると、「日本人の配偶者等」と記載された「在留カード」が交付され、日本への上陸・在留が許可されます。
なお、「在留資格認定証明書」の有効期間は発行日から3か月ですので、この期間内に日本へ上陸する必要があります。
また、万一、「在留資格認定証明書」を紛失した場合、再発行されませんので、取扱いには十分注意が必要です。
必要書類について
「日本人配偶者等」による在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
1 在留資格認定証明書交付申請書・・・1通
※ 申請書の用紙は、地方入国管理局で入手するか、入国管理局のホームページからダウンロードできます。
2 写真(4㎝×3㎝)・・・1枚
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された上半身の無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
3 日本人配偶者の方の戸籍謄本・・・1通
4 日本人配偶者の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・1通
5 本国(外国)の機関から発行された結婚証明書(中国の場合は公証書)・・・1通
※ 外国人配偶者の方が韓国籍の場合には、婚姻関係証明書が必要となります。
6 身元保証書・・・1通
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(通常は、日本人配偶者の方)がなります。
7 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・各1通
8 質問書・・・1通
※ 「質問書」の用紙は、入国管理局で配布されているほか、入国管理局のホームページからもダウンロード出来ます。
9 返信用封筒・・・1通
※ 長形3号の定型封筒(23.5㎝×12㎝)にあて先を明記のうえ、392円分の切手を貼付します。
10 スナップ写真・・・2~3枚
※ お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。
11 その他、必要に応じて入国管理局が提出を求める書類
※ 申請者によって結婚に至った経緯や結婚後の生活状況等が異なるため、入国管理局が「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するか判断するうえで必要な書類の提出を求められることがあります。
その他留意事項について
※ 各証明書は3か月以内に発行されたものであること。
※ 各書類は日本語以外のものは翻訳文を添付すること。
※ 提出書類はすべて原本とし、交付・不交付に関わらず、一切返却されません。
在留資格認定証明書が不交付となる7つの理由
「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するか否かは、婚姻の事実が実態の伴ったも のかどうかについて審査されます。
のかどうかについて審査されます。
単に、戸籍に婚姻を証する事実が記載されているからといって、それだけでは在留資格認定証明書が交付されるとはありません。
入国管理局に行きますと、よく在留資格認定証明書の不交付に対して申請者と担当官が押し問答している光景を見か けますが、申請者としては「日本人の配偶者等」の在留資格に該当することを申請者の側で自ら証明しなければなりません。
この証明が不十分ですと、在留資格認定証明書の不交付という扱いを受けることになります。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が不交付となる理由を過去の事例から整理・分離すると、以下の通りとなります。
<在留資格認定証明書が不交付となる7つの理由>
| (1) 結婚の信憑性に疑いがあるもの。 (2) 結婚そのものが法律上、有効に成立していないもの。 (3) 申請内容が虚偽によるものであること(虚偽申告) (4) 提出した資料の信憑性に疑いがあるもの(偽造文書等)。 (5) 外国人配偶者が入管法第5条で定めている上陸拒否事由に該当するもの。 (6) 外国人配偶者に法令違反があるもの。 (7) 安定的・継続的に「日本人の配偶者等」としての活動を行なうことが見込まれないもの。 |
とあります
(1)の「結婚の信憑性に疑いがあるもの。」とは、いわゆる偽装結婚の疑いを意味します。
たとえば、初めて出会ってから結婚に至った経緯(いきさつ)を説明する文章からは、二人の真摯な意思に基づく真実の結婚であるとは読み取れない場合や、結婚後の状況から夫婦の実態が認められないといったケースです。
(2)の「結婚そのものが法律上、有効に成立していないもの。」とは、結婚の手続に、何らかの法律上の誤りがあった場合です。
(3)の「申請内容が虚偽によるものであること。」とは、申請内容に嘘がある、いわゆる虚偽申請、虚偽申告のことです。
たとえば、初めて出合ったときの日時や場所、紹介者の有無などについて、嘘の申告をした場合です。
(4)の「提出した資料の信憑性に疑いがあるもの(偽造文書等)」とは、提出した書類が偽造されたものであったということです。
たとえば、所得証明書を偽造したような場合です。
所得省めなどを偽造した場合には(公文書偽造罪Iなどで罰せられる)ケースもありますので全体にやってはいません。
(5)の「外国人配偶者が入管法第5条で定めている上陸拒否事由に該当するもの。」とは、外国人配偶者が過去に一定の犯罪を犯して処罰を受けたり、退去強制処分を受けたため、一定の期間、日本への入国を認めない者に該当する場合です。
例として、過去にオーバースティをして摘発され、刑事裁判にかけられ有罪判決を受けて強制送還されたことがある場合です。
(6)の「外国人配偶者に法令違反があるもの。」とは、上陸拒否事由(好ましかる人物)に該当しないけれども何らかの法令に違反したことがあるケースです。
たとえば、観光ビザ(「短期滞在」という在留資格)で日本に滞在中に飲食店で働いていた(資格外活動に当る違反)といったケースがこれに当たります。
観光ビザは、あくまで観光を目的として発行されるビザでどれ以外の目的にぢ用できません。
(7)の「安定的・継続的に「日本人の配偶者等」としての活動を行なうことが見込まれないこと。」とは、日本における夫婦共同生活を送る上で、何らかの支障をきたすおそれのある事由が認められるということです。
たとえば、これから日本で夫婦共同生活を営むうえで必要な、①十分な広さの住居が確保されていないとか、②安定した収入または財産がないとか、③お互いの意思の疎通をはかる手段がない(言葉の問題)といった理由です。
結婚ビザの審査基準(許可要件)
<結婚ビザの審査基準(許可要件)>
- (1) 夫婦の真摯な意思に基づく実態の伴った結婚であること。
(2) 結婚が法律上、有効に成立していること。
(3) 申請内容が真実に基づくものであること。
(4) 提出した資料が権限のある発行機関が発行した真正な文書であること。
(5) 外国人配偶者が入管法第5条で定めている上陸拒否事由に該当しないこと。
(6) 外国人配偶者に法令違反がないこと。
(7) 安定的・継続的に「日本人の配偶者等」としての活動を行なうことが見込まれること。
これらの不交付の理由をもとに、入国管理局が考えている結婚ビザの審査基準(許可要件)の整理・分類すると、次ぎの通りです。
<結婚ビザの審査基準(許可要件)>
(1) 夫婦の真摯な意思に基づく実態の伴った結婚であること。
(2) 結婚が法律上、有効に成立していること。
(3) 申請内容が真実に基づくものであること。
(4) 提出した資料が権限のある発行機関が発行した真正な文書であること。
(5) 外国人配偶者が入管法第5条で定めている上陸拒否事由に該当しないこと。
(6) 外国人配偶者に法令違反がないこと。
(7) 安定的・継続的に「日本人の配偶者等」としての活動を行なうことが見込まれること。
結婚ビザの申請書は審査に当たる人の、目線で考える
結婚ビザの審査基準(許可要件)は、要するに結婚ビザの在留資格認定証明書が不交付となる理由の裏返しです。
そして、この審査基準(許可要件)を念頭におきながら、申請書の記入欄や質問書の質問事項を読んでいくと、より具体的なチェック項目が見えてきます。
たとえば、質問書の1ページ目に自宅の間取りを記入する欄があります。これは、これから日本で夫婦共同生活を営むうえで、十分な広さの住宅が確保されているか、というチェック項目です。
もし、現在、ワンルーム・マンションにお住まいであれば、入国審査官は、配偶者の方が来日したら、本当にそこで一緒に暮らすのか疑問に思うかもしれません。二人で暮らすには、ちょっと狭いですよね。
そこで、来日後は、家賃いくらくらいで、間取りはどれくらいで、どの辺りに新居を探すつもりであるといったあなたの考えを示す必要があります。
ここ迄に上げたチェック項目は、ほんの一例に過ぎませんが、申請書の記入欄や質問書の質問事項を注意深く読んでいくと、他にもたくさんチェック項目があることに気が付くはずです。
要は、申請書の記入欄や質問書の質問事項に書かれていることの意味をよく考え、そこからチェック項目を読み取ることが大切です。
結婚ビザの審査基準(許可要件)の内容や細かなチェック項目がわかったところで、今度は、各人の個々の事情をこれらのチェック項目と照らし合わせて、確認していきます。
そして、チェック項目にひっかかることがあれば、次に、それをどうクリアするか考え、それを文書で説明したり、必要に応じて資料を提出したりしていきます。
次に、審査基準の(1)の「夫婦の真摯な意思に基づく結婚であること」を例にとって、質問書の書き方のポイントをご紹介します。
質問書(申請理由書)の書き方のポイント!!
ポイント(その1)
まず、第1のポイントは、婚姻に至った経緯を「質問書」に具体的に詳しく記載する必要があります。
いつ、どこで知り合ったのか。初めて知り合ってから何故その後の交際に発展したのか。そして、何故結婚したいと思う ようになったのかということを具体的に、かつ正確に書きます。
単に、「平成○年○月頃、横浜市内の飲食店で知り合いました。その後、映画を見たり、ドライブにいったりしました。そ のうちにこの人と一緒になりたいと思うようになり結婚を決意致しました。」という程度の記載では不十分です。
ときどき、「交際期間が短いのですが、大丈夫でしょうか?」というご相談をいただくことがあります。交際期間が短いと、偽装結婚を疑われるのではないかと心配されて相談されてくるわけです。
しかし、どんなに交際期間が短かったとしても、いつ、どこで知り合ったのか。初めて知り合ってから何故その後の交際に発展したのか。そして、何故結婚したいと思う ようになったのか、ということは、交際期間が長い場合と何ら変わりありません。やはり、そのへんの事情をしっかりと説明することです。
「質問書」の詳しい書き方については、こちらをご覧下さい。 ⇒ 質問書の書き方について
ポイント(その2)
第2のポイントは、審査上、問題となる点を整理し、それに対する詳細な説明を別紙に記載して理由書を添付することが有効です。
何が審査上、問題となる点かということは、それぞれの事情により異なるため、一概にこれこれが問題となるとは申し上げられませんが、 「日本人の配偶者等」の在留資格を許可するうえで、審査官が懸念を抱くような事柄があれば、それに対する対応策を考え、審査上マイナスとなる点を補完する必要があります。
たとえば、課税証明書が提出できないのであれば、提出できない理由を説明し、それに代わる収入を証明する書類(給料明細書、預金通帳のコピーなど)を提出する、ということです。
<補完方法の一例>
1.○○である。(マイナス要因となる事項)
2.しかし、○○である。(マイナス要因をプラスに変える理由)
3.したがって、○○である。(プラス要因となる事項)
たとえば、収入が少ないとき(マイナス要因) ⇒ 実家で両親と同居するので家賃がかからない。(マイナス要因をプラスに変える理由)そのため、むしろ生活に余裕がある(プラス要因)、といった具合です。
ポイント(その3)
第3のポイントは、出来るだけ裏づけ資料を提出することにより、質問書や理由書等に記載した内容が真実であることを証明していくことです。
いくら質問書等に事実を具体的に、かつ正確に書いたとしても、審査官は書面を読んだだけでは、それが真実かどうかわかりません。理由書に記載したことが真実であることを申請者の側で証明していく必要があるわけです。
そこで、審査官を納得させるためにはある程度の裏づけ資料が必要となります。
たとえば、日本と本国とに離れて暮らしている間、電話や手紙によりやり取りしているのであれば、手紙や国際電話の通話記録の明細を提出します。
失敗しないための重要なポイントのまとめ
以上に紹介した内容が、みなさんに、是非、知っておいていただきたい重要なポイントです。
ここで、これを、もう一度わかりやすく整理すると
(1)結婚ビザの審査基準(許可要件)の内容を知り、よく理解する。
(2)申請書、質問書、必要書類等の中から、具体的なチェック項目を読み取る。
(3)ご自身の個々の事情をこのチェック項目と照らし合わせて、何か問題となる点はないかチェックする。
(4)問題点が見つかったら、それに対する対応策を考える。
(5)それらを文章にまとめ、必要に応じて追加資料を提出するなどして、入国審査官にわかりやすく伝える。
こう書くと、なんだかとても難しいことのように思われるかもしれませんが、これまでの経験上、審査において問題となる点は、せいぜい1つか2つ、多くても3つくらです。
要は、漏れのないよう、一つ一つ丹念に確認することが大切です。
在留資格認定証明書が不交付になったときの対処法
万一、在留資格認定証明書が不交付となってしまった場合、まず、不交付の理由を突き止める必要があります。
不交付の理由を調べるには、申請した入国管理局へ行き、その理由を詳しく聞きに行って下さい
そして、不交付の理由がわかり、その理由が再申請可能なものであれば、その理由となった事由を補正して、もう一度一から申請し直します。
査証(ビザ)が発給されないときの対処法
在留資格認定証明書が交付されたら、それを配偶者のもとへ送り、配偶者の方が現地の日本総領事館に査証(ビザ)の申請を行います。
そのとき、稀に査証(ビザ)の発給を拒否されることがあります。
そうなると、いくら在留資格認定証明書が交付されたとはいえ、日本に入国することはできません。
その場合、査証(ビザ)が発給されない理由を突き止める必要がありますが、入国管理局と違って、日本総領事館や外務省に問い合わせてしてみても、その理由は開示してくれません。
そのため、自分でその理由を突き止める必要がありますが、査証を申請したときに領事館から配偶者の方に確認の電話があったり、追加の資料の提出を求められたりすることがありますので、案外、そのときのやり取りや提出した資料の中に発給されない理由が含まれていることがあります。
そこで、そこから問題点を見つけ出し、査証が発給されない理由だと思われることがあれば、その点を補正して、再度、在留資格認定証明書の交付申請からやり直します。
なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
●結婚ビザが不許可になる例
●結婚ビザ(家族ビザ)
日本のビザの中には、日本人や永住者と結婚したときの配偶者ビザ、 その他のビザを持つ外国人と結婚したときの家族滞在ビザ、 日本人や永住者と離婚したときの定住者ビザなどのビザがあります。
子どものビザは基本的に外国人の親と同じビザです。
なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか?
日本では、大卒の高学歴外国人は就労ビザがもらいやすく、単純労働者は就労ビザがもらえないシステムになっています。
そして、就労ビザがもらえない外国人が、日本で働くために、形式的な結婚をしてビザを申請することが多いため、 入国管理局はすべての結婚ビザの審査において” この結婚は本物だろうか。” と疑っています。
観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更できるのは「特別な事情」がある場合だけ!
長期ビザ(結婚ビザや就労ビザ、留学ビザなど、日本に1年以上滞在できるビザ。)の申請をする場合には、外国人が日本に来る前に、 保証人が日本の入国管理局へ申請するのが一般的です。
ビザの申請が許可されると、” 在留資格認定証” がもらえますので、保証人が外国人に認定証を送り、 外国人が外国にある日本大使館で認定証を提出して、ビザの証印(スタンプ)をもらった後に日本へ入国します。
そこで、入国管理局は” 長期ビザが欲しいなら、観光ビザ(短期滞在)の期限が切れる前に帰国し、その後に長期ビザの申請をしなさい” と指導しています。
実際に、観光ビザ(短期滞在)から就労ビザへの変更申請は認められていません。
結婚ビザの場合、このように外国人が外国にいる間に申請をしてくれれば、入国管理局が嘘の結婚だと見抜いた場合には、ビザの申請を不許可にすることで、悪い外国人の入国を防ぐことができます。
| しかし、実際には、日本で働くことを目的として、嘘の結婚をした後に観光ビザから結婚ビザへの変更申請をする外国人や、 結婚ビザの申請が不許可になった後もそのまま日本で行方不明になってオーバーステイをする外国人があまりにも多いので、 入国管理局は” たとえ本当の夫婦だとしても、観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更を認めるのは、特別な事情がある場合に限る。” という方針で審査をしています。 |
観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更が認められる例
日本人と外国人との結婚で、以下の場合には、「特別な事情がある」と認められ、観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更することができます。
・幼い子どもがいる。(母親が外国人で父親が日本人)
→ 子どもの面倒を見るための「特別な事情がある」と認められる。
・まだ結婚していない。
→ 今回の短期滞在の間に日本で婚姻届を提出すると「特別な事情がある」と認められる。
・過去に結婚し、外国で婚姻届を提出したが、日本で婚姻届を提出していなかった。
→ 今回の短期滞在の間に日本で婚姻届を提出すると「特別な事情がある」と認められる。
・変更申請の前に認定申請をして、すでに許可証(認定証)を持っている。
→ 認定証を持って変更申請すれば「特別な事情がある」と認められる。
結婚以外の特別な事情が必要な場合
外国の日本大使館で観光ビザ(短期滞在)を申請した人(査証免除国ではない人)が、観光ビザから結婚ビザへ変更する場合、婚姻届を提出したことに加えて「結婚以外の特別な事情」を要求されることがあります。
「結婚以外の特別な事情」とは、例えば、妻が妊娠しているとか、幼い子どもがいて共働きができないとか、日本で家族が入院したので看病する必要があるとか、母国の治安が悪くて帰国できない、などです。
「結婚以外の特別な事情」がない場合には、結婚ビザへの変更申請が不許可になり、「婚姻届の提出は終わったんだから、一度帰国して結婚ビザの認定申請(審査が3ヶ月)をしなさい。」と入国管理局に指示されます。
アメリカやヨーロッパなど、ビザなしで来日できる国(査証免除国)の人は、結婚そのものが特別な事情として認められます。
そのため、「結婚以外の特別な事情」は要求されないことが多いです。
観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更できない例
以下の場合には、「特別な事情がある」と認められないため、帰国した後に結婚ビザの認定申請をするよう入国管理局から指導されます。
・以前に日本に滞在していた時など、過去に日本で婚姻届を提出した。
→ それだけでは「特別な事情」と認められない。
日本での婚姻届が終わっていれば、外国にいる間に結婚ビザを申請できるからです。
・外国人の日本での就職先が決まっている。
→ それだけでは「特別な事情」と認められない。
あくまでも” 結婚そのもの” に特別な事情が認められる必要があるからです。
・同じ国籍の外国人同士で結婚した。
→ それだけでは「特別な事情」と認められない。

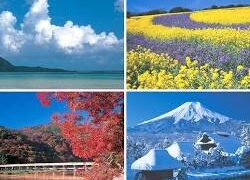

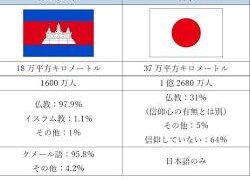
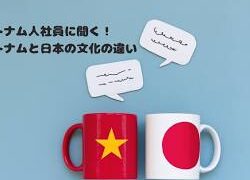
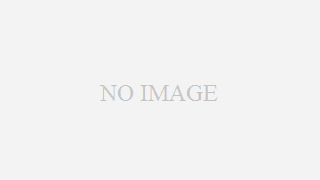















コメント